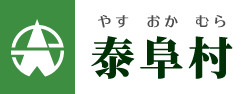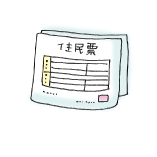昭和初期の未曽有の世界恐慌は当然のことながら日本をも襲い、中でも最大の打撃を受けたのが長野県。それは糸価、繭価の暴落によるところが大きい。とりわけ養蚕飼育密度の高かった下伊那地域においては深刻であり、泰阜村も例外ではない。
明治の末から泰阜村も養蚕が盛んになりほとんどの農家が養蚕農家になっており、土地がなくても食べていけるということで人口も増加していた。加えて、三信鉄道(現在の飯田線)やダム(泰阜発電所)工事の関係者が村に数多く入っており、当時の人口は5,000を超えていた。山村の貧村に襲いかかった恐慌により、農家は繭価の暴落による多額の借金をかかえ、昭和12年には村外へ約600余名が出稼ぎに出る状況に陥っていた。その窮地を救おうと村ではさまざまな経済更生計画がたてられたが、その中心となったのが満洲移民を軸とする計画であつた。
泰阜村の開拓の歴史と経過
- S12.10
満洲視察団を現地に派遣 - S13.7
満洲分村計画の実施を議会決定
第一次先遣隊 21名 渡満
- S14.2
団長渡満、入植式 大八浪開拓団結成 - S14.7~S14.11
71家族349名 入植 - S15.3~S15.7
185家族560名 入植 - S18.4
19家族52名 入植